
泌尿器科
腎臓
腎不全
症状
慢性腎不全では、病気の進行時期によって症状が大きくことなりますが、食欲はおおむね不振となりますが、症状が落ち着いている時と悪化している時ではその程度は差があります。
一般には食欲が落ちてやせることが多いようです。尿量は、全身の臓器の異常が見られる尿毒症などが起こらない限りは減少しません。むしろ一時的に比重のうすい尿がたくさん出ることがあります。ただし、わんちゃんの病気には多尿のものが多く、尿量が多いからといって腎不全とは限りません。
慢性腎不全では排尿が普通に行なわれているので、血中のリンの濃度が高くなりますが、カルシウムが吸収されにくくなるため骨が弱くなることがあります。吐いたり、下痢したりすることが常にあるわけではないですが、寝起きにはいたり、かるい下痢がつづいて見られることもあります。貧血はほとんどで見られます。
原因
慢性糸球体腎炎、間質性腎炎、水腎症などの病気によって、腎臓の中のネフロンが少しづつ壊れていくため、腎臓が働かなくなります。
治療
慢性腎不全ではゆ液と食事療法が中心となります。体内のたんぱく質分解をおさえるために、タンパク同化ホルモンを注射することもあります。リン吸着剤や、活性炭などの吸着剤を症例にあわせて処方します。その他にも症状によって追加の内科的治療を行ないます。食事療法はたんぱく質のコントロールと塩分を制限します。
カロリーはもちろんですが、他にも必要な栄養素をバランスよくとらなければなりません。たんぱく質は高品質のものを最小限に抑えて与えていきます。腎不全になった腎臓がふたたびもとにもどることはないので、残された腎臓をこれ以上悪くさせないように配慮しなくてはなりません。それには、わんちゃんの体にストレスが加わらないように注意することも大事です。
タンパク喪失性腎症
症状
なんとなく痩せてきた。なんとなくお腹周りが張ってきた。呼吸がおかしいなどの症状を呈することがある。
原因
感染性疾患、炎症性疾患、主要性疾患などが影響しているとされている。
主な原因を分類すると腎前性、腎性、腎後性があり、ヘモグロビン尿や、激しい運動、発熱、間質性腎炎、レプトスピラ感染等がある。
治療
基礎疾患の治療のほかに蛋白尿を減らす治療としてACEIの使用や、ARBの使用がされている。食事については可能であれば腎臓病の食事に切り替える。
また、腎臓の糸球体が原因となっている場合には免疫抑制療法を行う。
蛋白尿に起因した治療としては、凝固亢進、浮腫、高血圧、慢性腎臓病、急性腎臓病の治療である。
腎盂腎炎
症状
無症状の場合もあれば、敗血症症状といった重篤な症状を示す子もいる。
慢性では無症状だったり、多飲多尿を示す子もいる。急性では、しばしば発熱、食欲不振、無気力、嘔吐、腎臓の痛み等を伴う。腎臓の痛みが確認された場合にはこの病気を強く疑う。
片側だけのものでは無症状、無症候性のこともあるが、両側性では高窒素血症になることが多い。
原因
最も多いのが細菌感染である。他に真菌、ウイルス、寄生虫が認められることもあるが当院で確認できた細菌以外の感染はまだない。
治療
細菌感染が主体なので、抗菌剤を使用する。長期的の投与することが今現在では推奨されている。
腎結石のある子たちは、結石を除去しないかぎり本症は消失しにくい。
膀胱
膀胱炎
症状
発熱、食欲不振、元気がなくなるなど、病気の際の一般的な症状があらわれることがあります。
また、水をたくさん飲むようになり、排尿の回数がふえます。残尿感もあり、排尿の姿勢をたびたびとりますが、尿がでないことがあります。
ただし、尿が出にくいからといっても膀胱炎とは限りませんので注意しましょう。
排尿しようとしても尿が出ないときには尿道で石がつまってたり、前立腺肥大などで尿道が圧迫されてでずらくなっていることもあります。
健康な時の尿はうすい黄色で、にごりもありませんが、膀胱炎の際には尿が濃くなったり、にごったりします。
病気の程度によって色の濁りの程度は違いますが、ひどい時には、尿に血がまじったり、においがつよくなったりすることもあります。
原因
尿道から進入した細菌が膀胱に感染して炎症を起こします。膀胱炎は男の子より女の子に多く見られます。膀胱炎になると多くの場合、慢性化もしくは潜在化(細菌が増えずに生き続ける状態)します。
細菌の感染が尿路をさかのぼるように広がり、腎盂腎炎へ移行することもあります。細菌による炎症以外にも、結石やストレス、寒冷などからくる膀胱炎もあります。
治療
尿を検査し、細菌に対してもっとも効果のある薬を調べて治療法を決めます。その結果に応じて、抗生物質を与えます。
当院では、膀胱炎に対して迅速に対応するため尿検査の結果から、すぐに抗生剤を決め、頻回の散歩などをおこなって排尿回数を増やし、水分をしっかり取ってもらっています。抗生剤の効果がはっきり出ない場合にはすぐに培養検査を行い、薬剤耐性を調べ、症例ごとにあった抗生剤の投与を行なっています。
膀胱結石
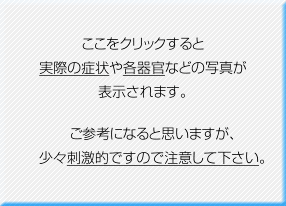
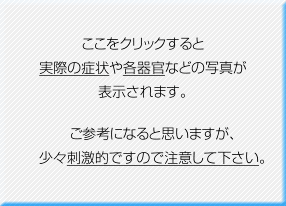
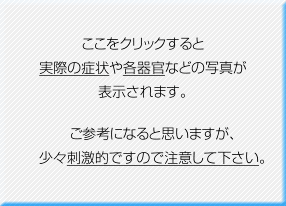
症状
膀胱に結石ができる病気。膀胱炎と同じような症状があらわれるが、膀胱炎よりも出血が多く見られる。残尿感があって排尿回数が多いです。血が長時間尿中にある場合は血液の成分が壊れて血色素がとけだすため、尿の色が紅茶色にかわることもあります。
原因
細菌感染による膀胱炎が原因のひとつと考えられています。また、食事中のミネラル成分や水分補給などが要因で、尿の濃度、ph、イオン強度が変動することにより結石を誘発しています。飲み水、食事等が影響しているので結石の出来やすいわんちゃんは食生活にも気をつけましょう。
また、副腎皮質機能亢進症等の病気によって2次的に結石をつくりやすくしている場合もあります。
治療
内科治療では、結石の成分が判明している場合は処方食の摂取や水分摂取を促すことにより尿成分やphを調整して欠席の溶出を促します。また、感染症が認められる場合は抗生物質の投与を行なう。しかし、結石が溶出しない場合などには外科的に結石を除去する必要があり、その後も食事などの管理が必要です。
また、2次的に結石ができやすくなっているこなどはもとの病気のコントロールが必要な場合もありますので注意しましょう。
一方で一部の子は飲水に使っている水をミネラルウォーターにしていることによって結石ができてしまった子もいるので口に入るものは問題ないか注意しましょう。
膀胱破裂

膀胱が破裂してレントゲン上で膀胱が確認できなくなっている
症状
元気がなくなったり、おしっこが出なくなったりします。
原因
交通事故や、転落などによって膀胱に外力が作用した場合に発生する膀胱壁の断裂です。
治療
造影により、造影剤の腹腔内への流出で確認します。外科的に損傷した膀胱壁の裂創を修復するとともに、腹腔の洗浄や抗生物質などによる腹膜炎の予防、尿毒症などへの対症療法が必要になります。